
「うちの子、とにかくキレやすくて……どうすればいいの?」
些細なことですぐキレる我が子に日々悩まされ、いったいどのように対処すればよいのかと途方に暮れていませんか?
相手はエネルギーを大量に持っている子ども。冷静に対処しようと思っても、我慢できずに感情的になってしまい、クタクタですよね。
「我が子だけがキレやすいのではないか……」と思う方も多いかと思いますが、子どもがキレるのは、自身の感情をうまく制御できないからです。
今回は、そんな子どものキレやすさを抑えるために、次の3つの方法をお伝えします。
| 【1】今キレている子どもへの対応を身につける 【2】次はキレないための感情コントロール方法を子どもに教える 【3】子どものキレを誘発する行動を控える |
過度に不安がる必要はありません。親のあなたが、お子さんの感情の交通整理をすることで、キレやすさは落ち着いていくでしょう。
ただし、実は、キレやすい子どもは、脳が栄養不足に陥っている可能性もあります。その場合は「5. キレやすい子どもは脳の栄養不足を疑ってみて」も要チェックです。
本記事では、専門家が提唱する理論に基づく、子どものアンガーマネジメント(怒りと上手につきあうための心理トレーニング)を元にした実践方法を紹介します。
難しくなく、今日から実践いただける内容です。ぜひお役立てください。
目次
1. 【心配不要】キレやすい子どもは脳が未発達なだけ

私たちの怒りをはじめとした感情のコントロールを司るのは、おでこ付近にある前頭葉。
この部位が十分に発達するのは、なんと20歳前後!発達には個人差もありますし、前頭葉がまだ十分に成長していない子どもは、キレやすくて当たり前です。
また、次に該当する場合、反抗期に差しかかっている可能性もあります。
・常時イラついた様子である
・親と目を合わせようとしない
・親から呼ばれたり話しかけられたりしても返事をしない
・何かにつけ親の言うことに突っかかってくる
いずれにしても、子どもにとっては自然なこと。そこまで心配する必要はありません。
2. キレやすい子どもへの対処は3つ

何かというとすぐにキレる子どもに対し、親が取るべき対処は次の3つです。
【1】今キレている子どもへの対応を身につける
【2】次はキレないための感情コントロール方法を子どもに教える
【3】子どものキレを誘発する行動を控える
どれか1つではなく、3つ全てを行いましょう。
子どもがキレている今この瞬間の対処と、キレない未来のための対処をセットで行うことで、初めて根本的な解決となるからです。
次にお子さんがキレてしまったときのことを考えると、「【1】今キレている子どもへの対応を身につける」から、順に覚えていくのがおすすめです。
では、次章から、上記3つの対処の実践方法について詳しく解説していきます。
3. 【対処1】今キレている子どもへの対応を身につける

まずは、今キレている子どもを落ち着かせる対処方法を確認しましょう。
キレた子どもを前にすると、「もう手に負えない……」と感じてしまいますよね。
でも大丈夫、下記の手順で子どもの気持ちをしっかりと受け止めれば、落ち着かせることができます。
| STEP1|子どもの感情を相槌を打って受け止める STEP2|子どもの欲求を言葉にする STEP3|実現方法を伝える or 親自身の状況や気持ちと見通しを伝える STEP4|お礼を伝える or 一旦離れてから話を再開する |
上記の手順は、 本田 恵子 (編著), 岩谷 由起 (著)『キレにくい子どもを育てる。親子のアンガーマネジメント』(講談社, 2021年)中で提唱されているコミュニケーション方法をもとに、より簡単に実践できるよう工夫したものです。
各ステップの具体的な進め方について、以下で順番に解説していきます。
STEP1|子どもの感情を相槌を打って受け止める
興奮状態にある子どもの言っていることは支離滅裂かもしれません。
しかし、よく話を聞くと、何らかの主張をしているはずです。その主張を、下記のように相槌を打ちながら聞きましょう。
「そうなんだね」
「そういう風に思ったんだね」
「悔しかったんだね」
自分の感情や思いを受け入れてもらえた、認めてもらえたというだけでも、子どもの気持ちは少し落ち着くはずです。
こちらから何か言いたいことがあっても、この段階では言わずに、子どもの感情をただ受け入れるのがポイントです。
STEP2|子どもの欲求を言葉にする
子どもの感情を受け入れたら、次は子どもの欲求を、下記のように言語化してあげます。
「◯◯がしたいの?」
「〜という風にしたいのかな?」
キレている子どもは、自身の欲求をきちんと言葉で言い表せないことにフラストレーションを感じています。言語化することで、そのもどかしさを解消してあげましょう。
子どもが「そうじゃない!」と否定した場合には、子どもの欲求を正しく言葉にできるまで、繰り返します。
STEP3|欲求の実現方法を伝える or 親自身の状況や気持ちと見通しを伝える
子どもの欲求を言葉にしたら、その欲求をどう実現すればよいかを伝えます。
ただし、いつでも子どもの望みを叶えてあげられるとは限りませんよね。その場合は、親自身の状況や気持ち、そして見通しを伝えましょう。
それぞれの具体的な対処方法については、下表をご参照ください。
| YESの場合 | 実現方法を伝えるか、複数の方法を提案する 「それなら、こうするといいよ」 「こんな方法があるよ」 「〜という方法もあるし、こういう風にしてもいいと思うよ」 |
| NOの場合 | (1)親の状況をアイメッセージで伝える 「私は今、◯◯をしているの」 「お母さんは〜という気持ちだよ」 (2)続けて、仕切り直しを提案する |
子どもの欲求の実現方法を伝える際は、あくまでも提案として伝えてください。
親の考えの押し付けとならないよう、最終決定は子ども自身に委ねるようにしましょう。
また、望みを叶えてあげられない場合にも、子どもの気持ちにとことん寄り添う姿勢を見せることも大切です。
STEP4|お礼を伝える or 一旦離れてから話を再開する
上記STEP3で子どもが落ち着けば、話を聞いてくれたこと、応じてくれたことに対し、「ありがとう」とお礼を言います。
興奮状態がなお収まらない場合は「どうしたらいいか、まだ考えがまとまらない感じかな?」などと子どもの気持ちに寄り添いましょう。
その後、「10分後にもう一度お話ししよう」と、一旦距離をおきます。
その上で、STEP1からの対応を再開します。
4. 【対処2】次はキレないための感情コントロール方法を子どもに教える

前章でご紹介した、キレている子どもを落ち着かせるための対処は、今困っている状況を打開できるという点で優先度が高いといえます。
ですが、次からはキレないようする未来志向の対処も同じくらい大切です。
そこで、怒りの感情と上手につき合う方法として近年注目されている、アンガーマネジメントを取り入れてみましょう。
怒りをただ抑えるのではなく、自身の感情が今どういう状態かを理解して、気持ちを適切に表現するアンガーマネジメントの考え方は、大人だけでなく子どもにも役立ちます。
ただし、大人向けの内容をそのまま子どもに習得させるのは難しいですよね。
そこで本章では、子どもが実践しやすいように工夫した下記の「怒りの感情のコントロール方法」をご紹介します。
| ・カッとなったら「6秒間待って」気持ちを落ち着かせる ・今の怒りの温度を確認する ・相手を許せるか許せないかを判断する |
全ての方法を行う必要はありませんので、どれか一つでも試してみましょう。
以下でそれぞれの方法について詳しく説明しています。キレやすいお子さんに「こうするといいよ」と教えてあげてください。
カッとなったら「6秒間待って」気持ちを落ち着かせる
カッと頭に血がのぼったら、そのまま怒りに任せて口から言葉を出す前に、6秒間待って気持ちを落ち着かせます。
怒りの感情のピークが持続するのは、長くて6秒といわれているからです。
つまり、カッとなってから6秒だけ待てれば、衝動をやり過ごせていくらか落ち着き、少なくともキレることはほぼなくなるのです。
6秒間の待ち方には、たとえば次のようなものがあります。やりやすいもの、気に入ったものを試してみましょう。
| ・6秒カウントする ・頭の中でごく短い歌を歌う(『メリーさんのひつじ』など) ・深呼吸する |
ただ、こうした方法を覚えたとしても、実際にカッとなったときに思い出して実践するというのは簡単ではないはずです。
親がその場に居合わせているときには、親から子どもに「6つ数えるんだったよね」「はい、深呼吸だよ」などと促して、習慣化を助けましょう。
今の怒りの温度を確認する
怒りの感情を10段階の温度計でイメージするのも効果的です。子どもが小さければ、もう少し大雑把に5段階くらいでもよいでしょう。
怒りといっても、ちょっとイラッとする程度の怒りもあれば、我を忘れてしまうほどの怒りもありますよね。
下図「怒りの温度計」を印刷したものを壁に貼るなどして、「今怒ってる気持ちは、1から10のこの温度計の、どのあたり?」と子どもに尋ねましょう。
参考:日本アンガーマネジメント協会 (監修), 篠 真希 (著), 長縄史子 (著)『イラスト版子どものアンガーマネジメント』(一般社団法人日本アンガーマネジメント協会監修, 2015年)を参考に筆者作成
「遊具の順番を並んで待っていたのに割り込みされた。5点くらいかな」
「描いていた絵を意地悪な子が取り上げて返してくれない。6点、いや7点だ!」
といった風に、自分の中に生まれた怒りの感情を数値化する過程で、子どもは自分を客観視することになり、ひとまず冷静になれます。
また、子ども自らが「振り返るとそこまで腹を立てることでもなかった」と気づくことも多いでしょう。
相手を許せるか許せないかを判断する
怒りの感情を相手にいきなりぶつける前に、相手を許せるか許せないか、考える習慣を身につけさせましょう。
たとえば、友だちが貸した本を約束した日までに返さなくて怒っている場合を想像してみてください。
「借りたものは約束の日までに返すべきだ」
という自分の考えに反して、相手の返却が遅れたから、腹を立てているわけです。
では、いつまでに返せば、あるいはどんな風に返せば「まあ怒るほどのことじゃないか」と許せるでしょうか?
今、腹を立てている相手のケースが次のどちらに当てはまるかを考えます。
・まあ許せる(ちょっとイラつくけど、怒るほどのことではないな)
・許せない(このまま何も言わずにおくわけにはいかない!)

「まあ許せる」のほうに当てはまると気づいたならば、もう怒る必要はありません。
「許せない」のほうに当てはまるとしても、自分の怒りを相手にどう伝えるかについて考えるきっかけになり、キレずに済むでしょう。
【対処3】子どものキレを誘発する行動を控える

親の言動が、子どもをキレさせてしまっているケースもあります。
子どもがキレる直接・間接的な原因となり得る親のNG行動には、以下のようなものがあります。
| ・頭ごなしに否定したり決めつけたりする ・相手を責めるような口調で問いただす ・質問の意図を把握できないと答えられない問いかけをする |
それぞれのNG行動について、以下でもう少し詳しく見ていきましょう。
頭ごなしに否定したり決めつけたりする
子どもの意見や考えも聞かず、否定したり決めつけたりすると、子どもはキレがちです。
頭ごなしに否定されたり決めつけられたりすれば、子どもは「言ったってどうせ聞いてもらえない」と思うようになります。
そして、話を聞いてもらえない状況でも自分の言い分を通すための方法として、キレることになるからです。
| 「ダメ!」 「そんなわけないでしょう」 「いつもそうなんだから!」 「どうせまた〜したんでしょ」 |
子どもがよりこたえているのは、自分の意見が通らないことよりも、言い分を聞いてもらえないことです。
結果的に自分の意見が通らないとしても、言い分を聞いてもらえ、納得できるように説明してもらえば、子どもには「キレる必要性」も「キレたくなる理由」もないのです。
相手を責めるような口調で問いただす
子どもを責めるような口調で問いただすと、子どもはキレやすくなります。
| 「なんでそんなことしたの?」 「どうしてできないの?」 |
そうした口調での質問は、質問の形を取った尋問に他ならないからです。
たとえば次のように言い換えましょう。
【例】
「なんでそんなことしたの?」 → 「何があったの?」
「どうしてできないの?」 → 「こうしたらできるようになるんじゃないかな」
質問の意図を把握できないと答えられない問いかけをする
その質問の意図がわからなければ答えられないような問いかけ方をしないようにしましょう。
| 「どうするつもり?」 「このままだとどうなると思ってるの?」 |
そのような問いかけ方は、子どもをキレやすい状態に追い込みかねません。
質問の意図を推し量らなくてならないはという困惑、うっかり変な答えはできないというプレッシャーに押し潰されそうになり、余裕がなくなるからです。
答えやすいよう具体的に、「どう(How)」ではなく「何(What)」や「どれ(Which)」などで、あるいはYESかNOかで答えられる形式で質問すれば、子どもを混乱させずに済みます。
【例】
「勉強どうするの?」→「宿題には何時から取りかかる予定かな?」
「学校はどうだった?」→「今日のお昼休みは何をして遊んだの?」
6. それでもキレやすい子どもは脳の栄養不足を疑ってみて

ここまで「子どもがキレやすいのは脳が未発達だから」という前提で、今キレている子どもを落ち着かせる方法や、今後キレないで済むようにするための方法をご紹介してきました。
しかし、子どものキレやすさの原因が「脳の栄養不足」に潜んでいる場合もあります。
なぜなら、私たちの脳で活躍する「セロトニン」が、栄養が不足するとうまく合成されなくなるからです。
| 【セロトニンとは?】 衝動性を自制し、精神状態を安定させる働きを担う神経伝達物質。 |
あくまで一つの可能性ですが、栄養不足を疑ってみるのも一つの手といえるでしょう。
セロトニンの合成に関わる栄養素には、下表のようなものが挙げられます。
【セロトニン合成に必要な栄養素例】
| トリプトファン | 必須アミノ酸の一種。大豆・豆製品、乳製品、肉、魚などのタンパク質に豊富に含まれる |
| ビタミンB群 | トリプトファンからセロトニンを合成する際に必要となる。玄米、小麦胚芽、レバー、青魚などに豊富に含まれる |
| 鉄 | トリプトファンからセロトニンを合成する際に必要となる。レバー、牛肉などの赤身の肉、青魚などに豊富に含まれる |
| マグネシウム | トリプトファンからセロトニンを合成する際に必要となる。海藻類に豊富に含まれる |
上に挙げた中でも、子どもに不足しがちといわれているビタミンB群と鉄の摂取を意識するとよいでしょう。
| 【サプリメントで鉄を摂取するならフェリチン鉄がおすすめ】 ビタミンB群と鉄を、日々の食事で十分に摂るのは難しいですよね。 そこで、サプリメントを上手に取り入れてみてはいかがでしょうか。とくに、サプリメントで鉄を補うのであれば、「第3の鉄」とも呼ばれるフェリチン鉄がおすすめです。
鉄のサプリメントといっても、さまざまな種類があります。 ・フェリチン鉄:吸収率は約30% お子さんの健康を考えて、ぜひフェリチン鉄のサプリメントを検討してみてください。 |
7. まとめ
キレやすい子どもに対し、親が取るべき対処は次の3つです。
【1】今キレている子どもへの対応を身につける
| STEP1|子どもの感情を相槌を打って受け止める STEP2|子どもの欲求を言葉にする STEP3|実現方法を伝える or 親自身の状況や気持ちと見通しを伝える STEP4|お礼を伝える or 一旦離れてから話を再開する |
【2】次はキレないための感情コントロール方法を子どもに教える
| ・カッとなったら「6秒間待って」気持ちを落ち着かせる ・今の怒りの温度を確認する ・相手を許せるか許せないかを判断する |
【3】子どものキレを誘発する行動を控える
| ・頭ごなしに否定したり決めつけたりする ・相手を責めるような口調で問いただす ・質問の意図を把握できないと答えられない問いかけをする |
本記事をご参考にしていただくことで、キレやすい我が子をどうすればよいかという皆様のお悩みが少しでも軽くなれば幸いです。
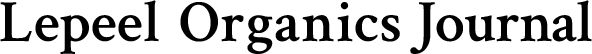


コメント